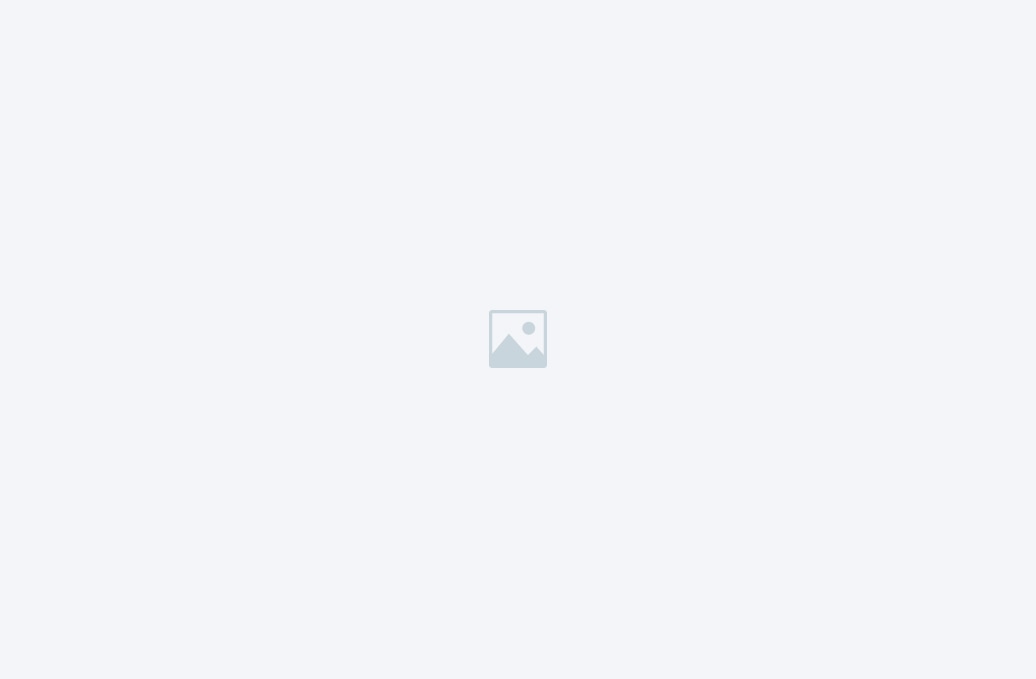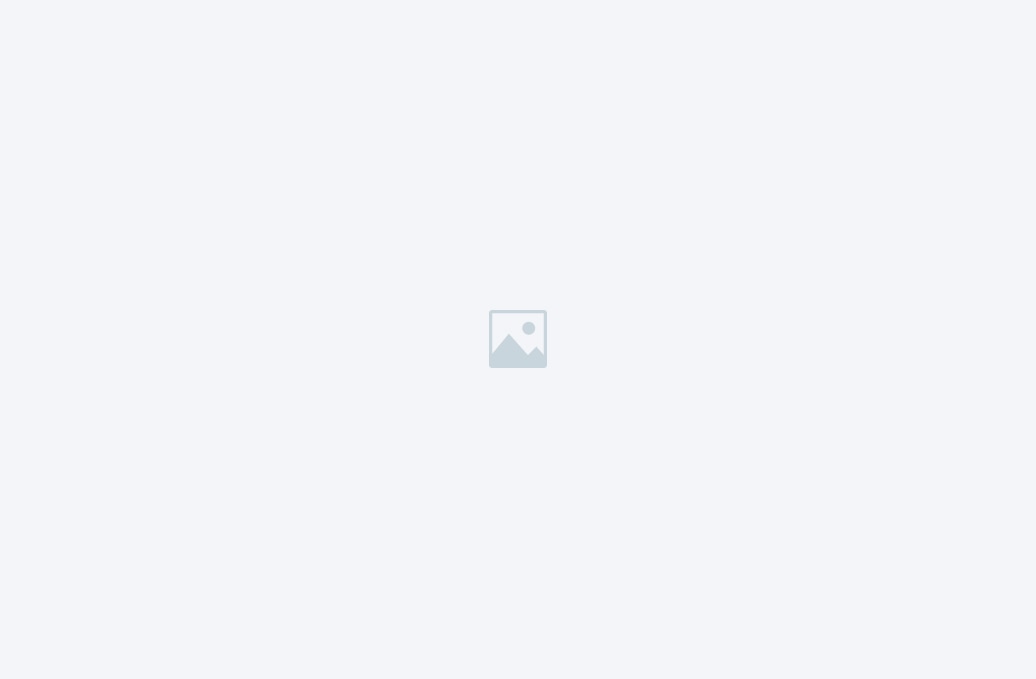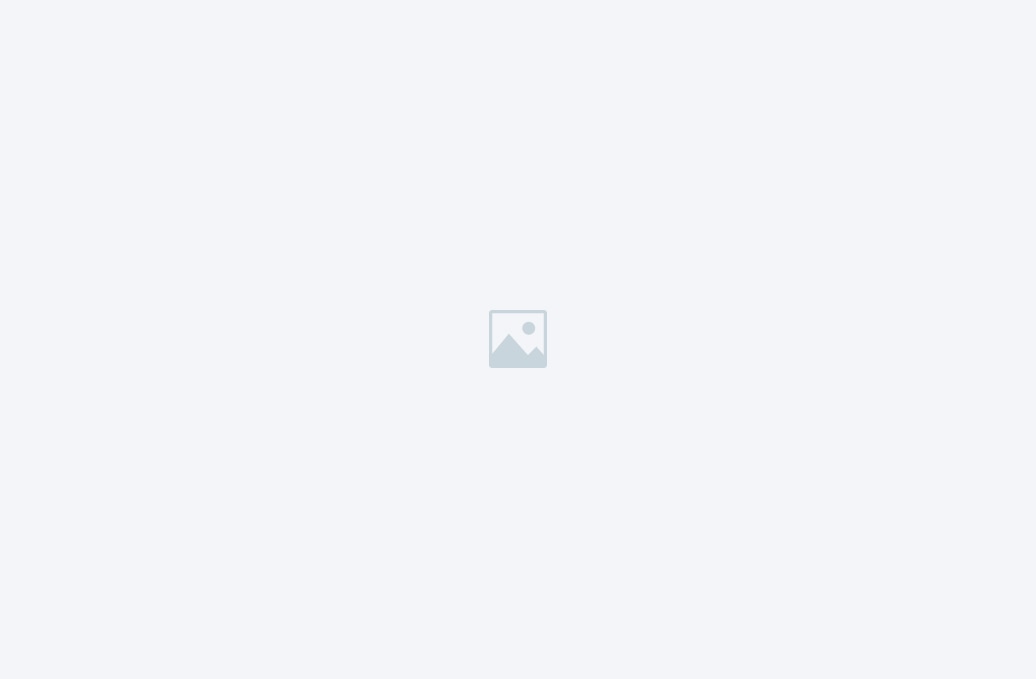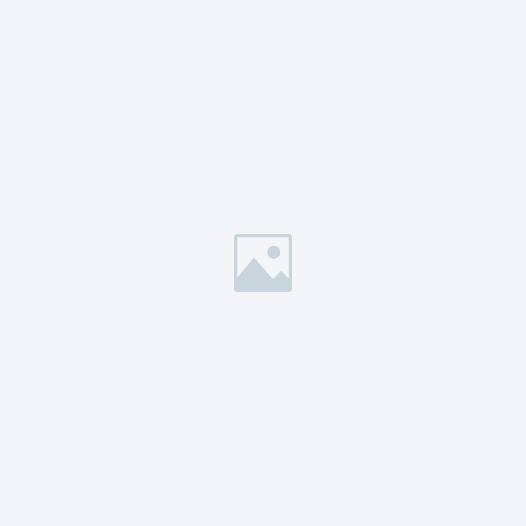清水康之セルフストーリー
― 森と風、手と音のあいだに ―
Ⅰ 幼少期 ― 音への最初の記憶
子どものころ、音楽の授業は得意ではありませんでした。
先生の声が少し怖くて、リズムを外すたびに心が固まってしまう。
それでも、リコーダーだけは好きでした。
家で吹くと、親が「上手だね」と褒めてくれました。
あの小さな瞬間の喜びが、後に音を生涯の友とするきっかけになったのかもしれません。
小学4年生のとき、担任の先生が亡くなりました。
「自分のいじめが原因だったのでは」と思い悩み、
心の奥に深い影を残しました。
その出来事は、音楽に向かう“心の理由”のようなものとして、
いまも静かに自分の中にあります。
中学校に進むと、時代の空気はどこか荒れていました。
社会全体に閉塞感があり、学校でもいじめが増え、
誰もが居場所を探していたように思います。
そんな中で、祖母の家が唯一の避難所でした。
何も言わずに隣に座り、お茶を飲む時間。
その沈黙が、何よりもやさしかった。
言葉を使わずに寄り添うこと――
のちに“音で寄り添う”自分の表現の原型が、すでにそこにあったように思います。
Ⅱ 青年期 ― 社会の歪みと葛藤
大学を出て最初に働いたのは、地方の工場でした。
品質管理の仕事。朝から晩まで響く機械音の中で、
人の声がどんどん小さくなっていく気がしました。
納期、ミス、報告、責任。
人が“人”としてではなく、“役割”として扱われていく現場。
「生きる」と「働く」が切り離された社会の歪みを肌で感じました。
そんな日々の中で、自分の中に「別の生き方を探したい」という
小さな願いが芽生えました。
Ⅲ ケーナとの出会い
転職を経て少し心が疲れていた頃、
偶然、街のカルチャーセンターで南米の笛「ケーナ」に出会いました。
最初に教えてくれたのは、日本人の先生でした。
温和で、音を“感じる”ことを大切にする方。
「音は競うものではなく、分かち合うもの」と教えてくれました。
音楽の成績が悪かった自分でも、ケーナは息を吹けば音が出る。
その素朴さと温かさが、自分の中の何かを目覚めさせていきました。
やがて、南米のフォルクローレに惹かれるようになり、
新宿駅前でペルーの路上演奏グループに出会いました。
彼らの吹くケーナの音を初めて聴いたとき、
全身に鳥肌が立ちました。
その音は、技術や理論を超えて、
「生きる」というエネルギーそのものでした。
中でも、ペルー人奏者セルヒオ・アウキッチャの
無言で語るような演奏に衝撃を受けました。
その瞬間から、わたしの人生の方向は変わっていきました。
Ⅳ 代々木公園の夜
それからというもの、夜ごと代々木公園や桜木町でケーナを吹きました。
音がなかなか出ず、冷たい風の中で何度も息が詰まりました。
それでも、吹くことをやめられませんでした。
ある夜、ホームレスの方が近づき、
100円玉を手渡してくれました。
「ファンになりました」と一言。
別の夜には、警備員が缶コーヒーをそっと置いてくれました。
その小さな善意に支えられて、
「音を出すことには意味がある」と信じられるようになりました。
Ⅳ-2 ホスピスでの初演 ― 音のはじまり
ケーナを習いはじめてしばらくして、
初めて人前で演奏したのは、上野のホスピスでした。
最初は「自分のような初心者が吹いていいのだろうか」と迷いました。
けれど、担当の看護師さんが「音だけでもきっと届きます」と言ってくださり、
静かな病室の一角で、そっとケーナを吹きました。
音は小さく、震えていました。
けれど、その場にいた方がふっと微笑んでくれた瞬間、
「音には意味がある」と感じました。
その体験が、わたしにとっての“音のはじまり”です。
上手に吹くことではなく、
“その人の時間に寄り添う音”を奏でたい――
そう強く思うようになりました。
そのとき感じた「生きることと、音を出すことの境界がなくなる瞬間」。
それが今も、演奏の根に流れています。
Ⅴ ケーナを教える ― 音の輪を広げる
やがて、自分もケーナを教えるようになりました。
最初は数人から、やがて口コミで広がり、
延べ2万人以上の方にケーナを指導するまでになりました。
わたしが大切にしているのは、
「うまく吹くこと」よりも「音を楽しむこと」。
息を吹いた瞬間に生まれる“その人だけの音”にこそ、価値がある。
一音一音の中に、人生が宿ると信じています。
Ⅵ 震災の地で
東日本大震災のあと、陸前高田や宮古を訪れました。
瓦礫の中、潮の匂いが混ざる静かな土地で、
ただ風の流れに合わせてケーナを吹きました。
それは慰問ではなく、「何が起きたのかを知りたい」という思いでした。
亡骸が眠るその大地で、
風と音がひとつになる瞬間がありました。
人の悲しみと自然の力の中に、
確かに“いのち”の気配を感じました。
Ⅶ 癒しの笛 ― 松江の病院で
神奈川から島根・松江の病院へ。
筋ジストロフィーの子どもたちが入院する病棟でケーナを吹きました。
彼らは目でリズムをとりながら、穏やかに笑ってくれました。
その笑顔を見て、音楽とは「癒す」ものではなく、
「ともに生きる」ことだと気づきました。
音は空気の振動であり、呼吸の共鳴。
その空間に“命のやりとり”が生まれるのだと思います。
Ⅷ 受け継がれる音 ― 「コンドルは飛んで行く」の曾孫
ある日、教室に日系ペルー人の高校生が訪れました。
「この曲、うちのひいおじいさんが作ったんです」と笑いました。
「コンドルは飛んで行く」の作曲者、ダニエル・ロブレスの曾孫でした。
偶然のようで、必然の出会い。
それ以来、この曲はわたしの人生の“軸”となりました。
どんな場所でも、どんなときでも、この曲を吹くと原点に還れます。
同じ頃、リンバージャックにも出会いました。
木でできた小さな人形楽器。
ただの人形ではなく、木の生命と人の手が奏でる「音の媒介者」。
形に囚われず、自由に動くその姿に、音楽の本質を感じました。
Ⅸ 吹禅 ― 一音成仏の境地
虚無僧尺八の世界に触れたことで、音への理解が深まりました。
竹そのものを吹く素朴な尺八。
息のわずかな揺らぎが音の命を決め、
その一音の中に、心と自然が共にあることを感じました。
わたし自身も虚無僧笠をかぶり、
旅先で即興的にロ(ろ)吹きをします。
音を通して、自分の心が空気や風とひとつになる瞬間があります。
吹禅とは、悟りではなく「そうありたい」と願う心の姿勢です。
音は息のかたちであり、息は生きること。
音を出すことは、生きることそのものです。
その探求の中で、
南方熊楠の「萃点(すいてん)」――
万物が交わり、重なり合う一点の思想に共鳴するようになりました。
さらに、禅の静けさ、道教の自然観、ネイティブ・アメリカンの生命観、
そして縄文文化の「自然と共にある知」にも学びを見出しています。
ニクラス・ルーマンの社会システム論もまた、
人と人、自然と社会、音と沈黙が絶えず関係しながら
世界を自己生成していく構造を示しています。
それは、音楽の本質にも通じます。
近年は、古武術や不耕起栽培など、
“自然の理にかなった身体と暮らし”の在り方にも興味を持ち、
学びを続けています。
それらはすべて、音と同じく「無理をしない動き」「調和の感覚」へとつながっていく。
知識としてではなく、体験として感じとりたいと思っています。
これらの思想の学びは今も継続中で、
吹く音のひとつひとつが、わたしにとって“学びの延長線”です。
Ⅹ 問いかけとしての音 ― 横浜カジノ反対運動のなかで
コロナ禍の中、横浜のカジノ誘致に反対する活動に関わりました。
プラカードを掲げる代わりに、音で問いかけるスタイルを選びました。
昼の街に響くダブステップの重低音。
虚無僧笠をかぶり、サイケなDJスタイルで街を歩きました。
不思議な光景でしたが、子どもたちが笑顔で手を振ってくれました。
また、別の市民イベントでもケーナを演奏しました。
緊急事態宣言の中、街の人々の顔には不安と疲れが見えました。
けれど、演奏を終えたとき、ひとりの方が近づいてきてこう言いました。
「音楽が聞こえて、少し日常が戻った気がした。」
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥にあたたかな灯がともりました。
音楽は“特別なこと”ではなく、“日常を取り戻す力”でもある。
そのことを改めて実感しました。
その後、首相官邸前でもケーナを吹きました。
緊張した空気の中で、「主張するより、音で語る」という自分の在り方を確かめました。
結果として多くの署名が集まり、カジノ計画は中止になりました。
自分の力は小さくても、音には確かに人の心を動かす力があると感じました
Ⅺ 放課後デーサービスで
現在、放課後等デイサービスに勤務しています。
音楽を教えているわけではありません。
子どもたちと共に過ごす中で、
「いのちとは何か」「生きるとは何か」を改めて学んでいます。
笑い声が響くとき、
どんなに小さな空間でも希望が生まれます。
彼らと過ごす日々は、わたしにとって音楽以上の学びの場です。
Ⅻ TAP & WIND ― 森と風、手と音のあいだに
リンバージャックとの出会いが、TAP & WIND の出発点でした。
木と手、風と音――そのつながりが、人をつなぐ象徴になりました。
教育や福祉の現場で出会う“大人の子どもたち”。
子どもの頃の傷を抱えながらも懸命に生きる人たちとの関わりを通じ、
“セルフ・コンパッション(自分への思いやり)”の大切さを学びました。
自然と人、手と音、心と社会。
そのあいだにある“つながり”を見つめること。
それがTAP & WINDの理念です。
ⅩⅢ 森と風の哲学
音楽も社会も、光と影のあいだにあります。
どちらか一方だけを見ても真実は見えません。
かつて経験した社会の闇に感謝はできませんが、
あの現場で見た人間の弱さや矛盾が、
いまの音に深みを与えてくれたのは確かです。
光と影、その両方を受け入れながら、
わたしは今日も笛を吹きます。
森と風、手と音――そのあいだに、
確かな“いのちの響き”を感じながら。
🪶 補記
現在、弁理士試験の勉強を続けています。
音やクラフトといった創作を「知の領域」からも守りたいという思いからです。
法と表現、知と自然、その橋を架けるような活動を目指しています。
(代表:清水 康之/TAP & WIND)