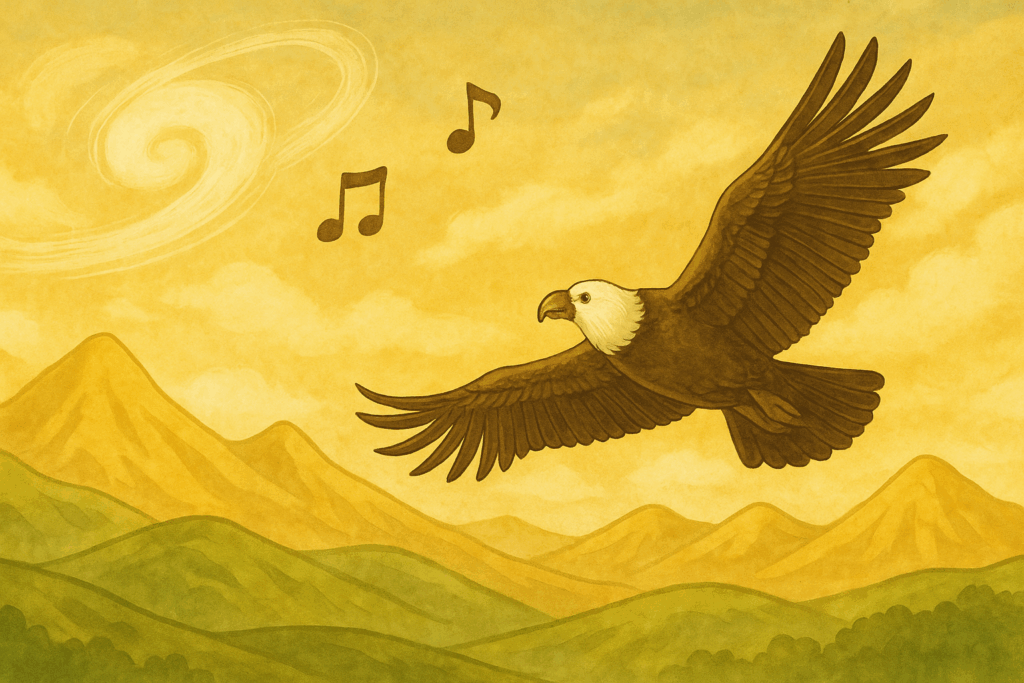コンドルは飛んで行く ― 風の通り道
Ⅰ 最初の記憶
小学校の音楽の授業で「コンドルは飛んで行く」を演奏した。楽器は木琴だったか鉄琴だったか覚えていない。音を間違えないように叩いたことだけが残っている。発表会のあとの空気も、拍手も覚えていない。ただ、音が消えた瞬間の静けさだけが残った。
子どもの頃、音楽は「正しくやるもの」だった。間違えないようにすることが目的だった。でもそのとき、なぜか“音が消える瞬間”だけに意識が残った。なぜだろう。その空白の時間に、何かがあったように感じていたのかもしれない。
Ⅱ 町工場の現実
大学で法学を学び、人の自由や尊厳について考えていた。けれど、卒業後に働いたのは群馬の町工場だった。プラスチックの焼ける匂い、上司の怒鳴り声、終わらない夜勤。同僚がひとり亡くなった。そのことを誰も話題にしなかった。日常は何も変わらなかった。
働くことの意味を考えたが、答えは出なかった。そのうち、心が動かなくなっていった。それでも生きるために働いた。けれど、心のどこかで別の道を探していた。
Ⅲ 横浜での夜
群馬の工場をやめて、転職した会社に騙される形で横浜に来た。話が違うと気づいたときには、もう遅かった。仕方なく働きながら、部屋で過ごす時間が増えた。
その頃は、よく夜に目が覚めた。夢の中でうなされたり、息が苦しくて眠れなかった。理由は分からないが、体が常に緊張していた。朝になっても疲れは取れなかった。
ある日、楽器店でケーナを買った。1万円ほどのボリビア製のものだった。吹いても音は出なかった。それでも、何度も息を入れた。うまく鳴らないのに、やめようとは思わなかった。
夜になると、海の近くの公園に行った。ケーナを持って、ひとりで練習した。風が強い日もあったが、関係なかった。音は出たり出なかったりした。でも、吹いていると、少しだけ呼吸が落ち着いた。
息を入れると、音が出ることもあった。出ないときもあった。それでも、その時間だけは、呼吸をしている実感があった。
音を探していたというより、呼吸を取り戻していたのかもしれない。